節分にはなぜ「豆」を使うの?あなたの知らない豆まきのおはなし

毎年2月になるとやってくるのが鬼、ではなくて節分ですね。
節分といえば幼稚園で作った鬼のお面をお父さんにかぶせ、「鬼はそと、福はうち」とはしゃいだことが懐かしく思い出されます。
ですが、あまり深く「節分」について考える機会はありませんよね。
「豆まき」や「恵方巻き」それはなぜ始まったのでしょうか?
今回は「豆まきの歴史や由来、作法など」をひも解いていきたいと思います。
Sponsered Link
節分の歴史。豆まきのルーツは?
さて、むかしむかしのお話です。
そもそも、節分とは季節の変わり目を意味します。
そして季節の変わり目には、邪気が入りやすいと考えられていました。
そこで宮中では、邪気を払うべく「追儺=鬼やらい」という行事が慣例となり、節分の夜に弓矢などで悪魔を追い払っていたそうです。

では、なぜ季節の変わり目の中でも、この時期だけに鬼やらいをするようになったのでしょうか。
日本では「立春」「立夏」「立秋」「立冬」により、季節の変わり目を表してきました。
むかしはその中でも「立春」がもっとも重んじられていたのです。
このことから、「邪気が入りやすい季節の変わり目」に行う行事として始まった鬼やらいは、「立春の時期」として定着しました。
追儺(おにやらい)は中国から伝わった文化で、文武天皇の時代(飛鳥時代)に執り行われたのが最初だといわれています。
文武天皇といえば、15歳で即位し、25歳という若さで崩御しています。
しかし、10年あまりの間に、大宝律令を頒布して律令の整備に努めたり、薩摩・種子島を征討し版図を拡大するなど、後の世の中にも多大な
影響を及ぼす事業を成し遂げました。
温厚かつ勤勉で、中国の書籍にも明るかったということなので、追儺(おにやらい)の導入にも頷けますね。

また寺社でも、おなじく邪気払いとして「豆打ち」を行っていました。(これも節分の夜です)
後にこの豆打ちは、宮中で行われていた追儺(おにやらい)と合体した行事となります。
江戸時代には今のスタイルが出来上がり、民間にも広まりました。
一方、節分に「恵方巻き」を食べる習慣は関西地方、とりわけ大阪が発祥の地だと言われています。
豆まきと同じく、邪気を払い一年の無事を祈るための行事として、広く普及しました。
関連記事:「恵方巻」今年の恵方が決定!なぜ恵方巻は始まったの?その由来」
豆まきの作法

さて、歴史の長い豆まき。
宮中や寺社の慣例行事だったこともあり、正しい作法が存在しますが、これらはしっかりと受け継がれてきました。
ですから、現在一般的に行われている豆まきの方法は、実はむかしとほとんど同じなのです。
皆さんご存知のやり方が、立派な作法なのです。
ではここで、おさらいしてみましょう。
豆まきには炒った豆を使う
炒る=射るの語呂合わせです。
夜に行う
鬼は、人々が油断しやすい夜にやって来るとされています。(幼稚園などで園内行事として行う場合は昼間にしますが、家庭では今でも夜に行うのが一般的ですね)
「鬼はうち、福はそと」と唱える
諸説ありますが、鬼=人の心に住む悪い気持ちを指す場合、その悪い心を外に出すために唱えるのだそうです。このあたりは、寺社の影響の名残かもしれませんね。
豆をまくのは一家の主人か年男・年女
邪気払いは厄払いと合致するためです。(これは現代とは違いますね)
最後に豆を食べる
1年の厄よけを願い豆を食べます。
では、豆を食べる数は・・・あなたの年齢?
次章で説明したいと思います。
Sponsered Link
節分の豆は自分の年齢の数より多く食べる?

実は当初は、自分の年齢よりも1~2個多く食べるとされていました。
これは、豆まきが始まった頃は「数え年」が主流だったからです。
数え年は「生まれた年を1歳とし、年が明けるとさらに1歳年を取る」という考え方です。
例えば12月に生まれた人は、大晦日までは1歳ですが、すぐに年が明けるのであっという間に2歳になるのです。
ですから、節分の時は生後2ヶ月程度であるにもかかわらず「2歳」ということになります。
さすがに豆は食べれませんね・・・
なので今では普通に実年齢で食べることが多くなりました。
好きな数で食べることをおすすめします。
なお、食べきれないときは、「福茶を飲む」でもOKだそうです。
☆まとめ☆
関連記事:「恵方巻」今年の恵方が決定!なぜ恵方巻は始まったの?その由来」
壬生寺の節分祭、日程・行事 やぜんざいや屋台で楽しさいっぱい!
「鬼」は古くから、悪しきものだとされ、桃太郎や一寸法師など、主役の敵は「鬼」であることが多いですよね。
今でも「悪い子」にしていると鬼が来ると子どもに信じ込ませる風習が残っている地域もあります。
豆まきの風習は、古来より「幸せや平和を願う人々の気持ち」が変わっていない、ということの表れなのかもしれませんね。
Sponsered Link
関連記事
-

-
七夕の空に「かささぎ」が舞う!2人のための橋渡し、その正体は?
七夕の主役と言えば「織姫と彦星」。(「織女と牽牛」とも言います) この2人は七夕の日に何をする
-

-
若草山の山焼き 選りすぐりのスポットを紹介! 鹿は大丈夫?
奈良の「若草山の山焼き」。 全国的に有名な奈良の名物になっています。最近では10万人近
-

-
高崎だるま市2017年は高崎駅西口駅前通り。その内容と少林山は?
「高崎だるま市」は少林山達磨寺で、毎年1月6日・7日に開催されていました。 「七草大祭
-

-
「犬っこまつり」でワンちゃんと雪まつり!ペット可のホテル情報満載!
秋田県湯沢市で毎年行われる「犬っこまつり」。 愛犬と一緒に雪まつりに参加できます!
-

-
2017壬生寺の節分祭日程と行事。ぜんざいや屋台で楽しさいっぱい!
節分の日は幼稚園や小学校で豆をもらったり、鬼の面を作ったり、家で恵方巻を食べたり・・・
-

-
津南雪まつり 厳選の宿とアクセス、知っておきたい注意点
「津南雪まつり」と言えば「スカイランタン」。 雪まつりの詳細やスカイランタンの魅力と参
-

-
節分は大阪の成田山で! ~豆まきを芸能人と楽しむポイントは?~
毎年人気芸能人が豆まきに参加することで有名な、大阪の成田山別院の「節分会」に参加されたことは
-

-
「西宮神社 十日えびす」混雑状況や行事は?~失敗しない2017版~
初詣が終わればすぐに「十日えびす」が開催されます。 十日えびすといえば「商売繁盛」を願
-
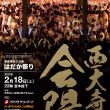
-
西大寺のはだかまつり アクセスと交通規制は?周辺のホテルについて
引用:http://www.okayama-cci.or.jp/ 岡山
-

-
湯西川温泉 かまくら祭り アクセスや宿情報!幻想的かまくらの世界
「湯西川温泉のかまくら祭り」 夜になると一面の銀世界に作られたかまくらに灯りが灯り、と