お彼岸のマナー。知っておきたいお墓参りと訪問の常識!

「お彼岸」の行事は、はるか昔、飛鳥時代の聖徳太子の頃から始まった、または聖徳太子が考えたと言われています。
仏教行事ですが、日本固有の風習です。
お彼岸について堅苦しい考えは無用ですが、最低限のマナーについては知っておきたいですよね。
今回は「お墓参りや、お供え物、訪問する際などのマナー」について調べました。
Sponsered Link
そもそも、お彼岸とは?
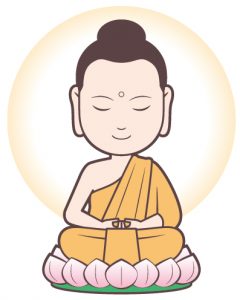
先ほども書いたように、お彼岸を行事として行うのは日本固有の風習なのですが、「彼岸」は古代インドの「波羅蜜多(パーラミター)」が語源で「彼の岸へ至る」という意味です。
彼方にある岸=彼岸は「すべての煩悩が消えた悟りの境地」のことを指します。
逆に、私たちがいるこちら側を「此岸(しがん)」と言い、「俗世間」のことを指しています。
彼岸は西、此岸は東にあるとされています。
お彼岸は真東から太陽が昇り、真西へ沈むので、彼岸と此岸が通じやすくなると考えられ、これがお彼岸行事の発祥となったのです。
ちなみに「お盆」はご先祖様をお迎えする行事ですが、「お彼岸」はこちらから「彼岸」へ近づくための修行として始まったそうです。
2017年のお彼岸はいつ?
実はお彼岸の日にちは毎年同じ・・・ではありません。
お彼岸は春と秋の年に2回あり、どちらも7日間あります。
まず春ですが「春分の日を真ん中とし、その前後3日間」を「春彼岸」と言います。そして秋は「秋分の日を真ん中とし、その前後3日間」を「秋彼岸」と言います。
春分の日と秋分の日は、国立天文台によって地球の動きや引力などを元に、緻密な計算をされて決定されます。
2017年の春分の日は3月20日、秋分の日が9月23日と発表されました。
という訳で今年のお彼岸は・・・
●春彼岸
| 彼岸の入り | 3月17日(金) |
| 3月18日(土) | |
| 3月19日(日) | |
| 春分の日 | 3月20日(祝) |
| 3月21日(火) | |
| 3月22日(水) | |
| 彼岸明け | 3月23日(木) |
●秋彼岸
| 彼岸の入り | 9月20日(水) |
| 9月21日(木) | |
| 9月22日(金) | |
| 秋分の日 | 9月23日(祝) |
| 9月24日(日) | |
| 9月25日(月) | |
| 彼岸明け | 9月26日(火) |
このような日程になります。
「春分の日・秋分の日」だけでなく、彼岸の入り~彼岸明けまでの間が「お彼岸」となるのですね。
お墓参りの仕方。作法とマナーについて

服装は派手すぎたり、だらしないものは控えましょう。お墓の掃除を考えて、動きやすい服装を選ぶと良いですね。
●掃除
・金属製でないタワシ(細かい部分は、歯ブラシが便利です)
・タオル
・ほうき
・ゴミ袋
・軍手
●お参り
・お線香
・ライター(お線香用のライターがあれば便利です)
・そうそく
・数珠
●お供え
・花
・故人の嗜好物
・半紙や紙皿(お供え物を乗せるもの)
2.手を洗い、バケツや手桶に水を入れる
3.掃除をする前にお墓の前で手を合わせて拝礼する
4.お墓を掃除する
5.お線香、お供えをしてお参りをする
お参りの方法は堅苦しく考えなくて大丈夫です。
持参している場合は数珠をして手を合わせ、座ってお参りしましょう。
お墓参りの時間は午前中が一般的ですが、午後からでも問題はありません。お寺や霊園に迷惑にならない時間帯にしましょう。
「墓石に水をかける、かけない」「ろうそくを使う、使わない」「ろうそくの火は消して帰る、付けたまま帰る」など、細かい違いは様々あるようですが、大切なことは、ご先祖様、故人へ感謝や愛情を持ってお参りすることです。
宗派などによっても違いはありますので、気になる点は親族の年長者や、菩提寺の住職に聞くなどしてくださいね。
献花は香りの強いもの、トゲがあるもの、毒があるものは避けてください。
お供え物が食べ物の場合は、持ち帰るようにしましょう。
もちろん、ゴミやバケツに残った水はきちんと処理をし、借りたものは所定の場所に返して、気持ちよく帰るようにしてください。
相手宅へ訪問する際のマナー
相手のお宅へ訪問してお参りする際には、必ず事前に連絡を取り了承を得ましょう。
できるだけ相手の都合に合わせるようにし、誰と何人で訪問するのか伝えておくようにしてください。
服装は、相手との関係性にもよりますが、落ち着いたスーツやワンピースが好ましいです。
お供えする品を持参し、掛け紙は「御供」と書き、包装紙の上から掛け紙をする(外のし)が一般的です。
水引は白黒の「結びきり」か「あわじ(あわび)結び」を使用します。

現金を包む場合は祝儀袋に「御仏前(御佛前)」と書くようにしましょう。
金額も故人との関係によりますが、近しい親族でなければ品物でも現金でも、3000~5000円程度が相場のようです。
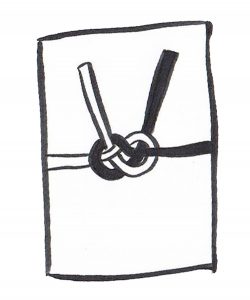
両方用意するなら、御供を2000円、御仏前を3000~5000円くらいにすると良いです。相手に気を遣わせることになりますので、あまり高価にならないようにするのがマナーです。
お供え物は、お花やある程度日持ちのする菓子などを持参すると良いでしょう。
☆終わりに☆
本来であれば、折に触れお墓参りできればよいのですが、なかなか出向く機会が少なくなってしまいがちです。
聖徳太子はそんな現代になることを見越していたのでしょうか?
ご先祖様や故人に思いを馳せ、日頃の感謝の気持ちを伝えたり、何気ない出来事を報告したりする良いきっかけにしたいですね。
Sponsered Link
関連記事
-

-
初詣に行こう♪ 「神社」と「お寺」の作法 あなたも格付けマスターに!
「初詣」というと、「神社」を想像する人が多いのではないでしょうか? 少なくとも私はそう
-

-
洋食のテーブルマナー あなたの食事方法は大丈夫?
ナイフ・フォーク、ナプキンの次は、いよいよ食事編です。 ここでは、「スープ」「パン」「肉」「魚
-

-
テーブルマナーに困ったら・・・ナイフとフォークの使い方
大好きな彼との記念日に、ちょっと奮発して憧れのフレンチレストランへ。 お化粧もコーディネートも
-

-
【初詣】 いつまでに行くの?喪中の時は? 役立つ知識の泉♪
毎年私にとって、新年を迎えて最初の行いは「初詣」です。 大晦日の夜に自宅近くの神社に向
-

-
洋食テーブルマナー。意外と知らないナプキンの使い方
以前は「ナイフとフォークの使い方やマナー」についてご紹介しました。 そちらをマスターしたら、次は「